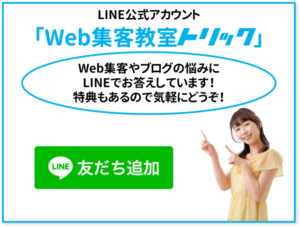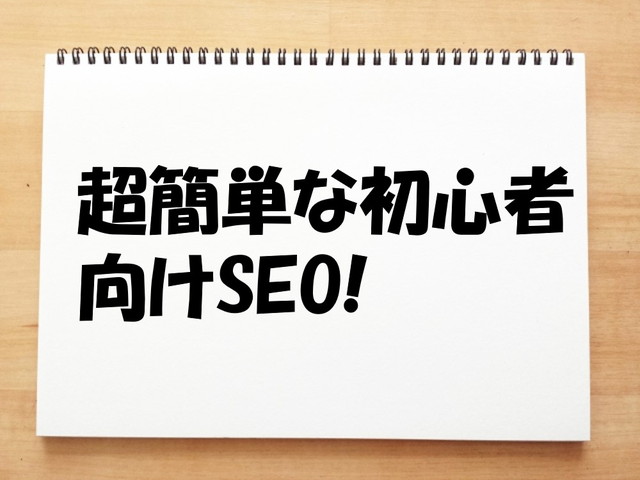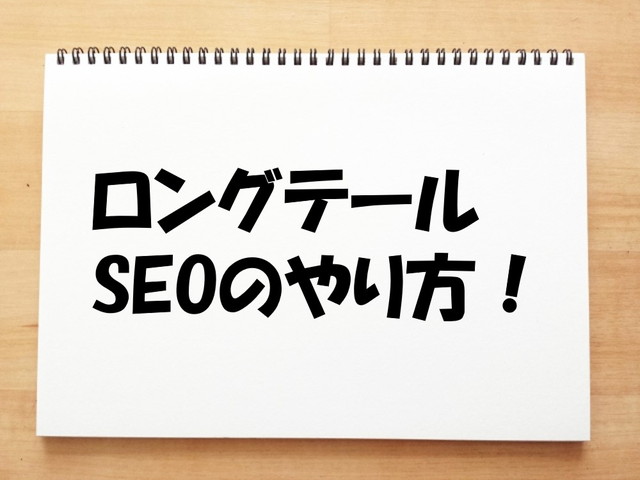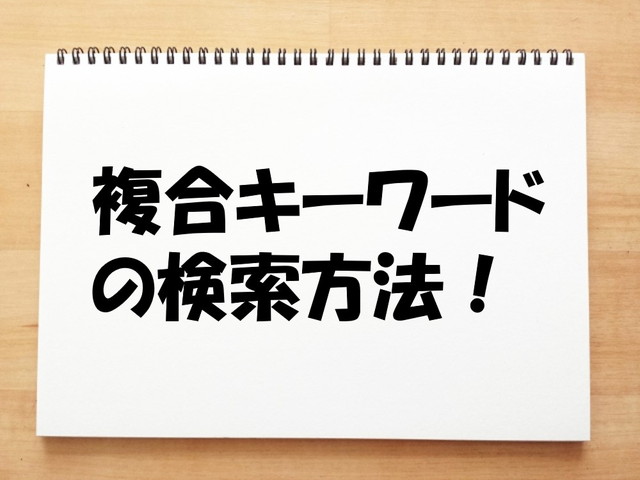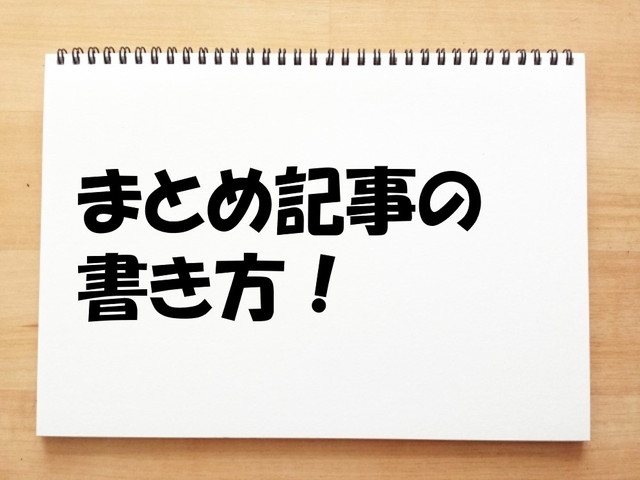ブログを運営には、SEOが大事って言いますよね。
一言でSEOって言っても、キーワードや被リンクなど、様々な要素があります。
いったい何から対策すれば良いのか、分からなくなるかもしれません。
でも、実はSEOって究極的には、難しいことなど何もないんです。Googleがやりたいことは、検索した人が良いと思う記事を上位表示させることだからです。
だから、人間が読んだ時に、満足できる記事を書いていれば良いんです。じゃあ、満足できる記事って、どのようなものなんでしょうか?
そのカギになるのが、ユーザー動向データです。良い記事を読んだ時に、人間は必ず何かアクションを起こすものです。
私たちはそのようなアクションを起こさせる記事を、書けば良いだけなんです。これが分かれば、SEOが分かったも同然です。
どのような記事を書けば良いか、もはや迷うことが無くなるはずですよ!
というわけで、この記事ではユーザー動向データの重要性とユーザーにアクションを起こさせる記事のポイントを説明しちゃいます。
もくじ
ユーザー動向データとは?
ユーザー動向データという言葉は、あまり聞き慣れないのではないかと思います。
ユーザー動向データとは、あるユーザーが検索エンジンで検索してから、記事を読み、ブラウザを閉じるまでの閲覧行動のことです。
でも、SEOを考えた時に、なんでこれが重要なんでしょうか?
記事の評価はユーザー動向データで決まる

最近はAIが発達してきたとはいえ、検索エンジンが人間のように記事の良し悪しを、分析することは無理です。
そこで、Googleはユーザーの一連の検索行動を分析して、どの記事がユーザーを満足させているのかを分析していると言われています。
例えば、あるキーワードで検索した時に、記事Aを30秒間読んでから、記事Bを4分間読んでブラウザを閉じたとしたら、どうでしょう?恐らく記事Aを少し読んで不満だったので、記事Bの方をじっくり読んだと考えられます。
逆に記事Aを4分間読んでから、記事Bを30秒間読んでブラウザを閉じたとしたら、どうでしょう?記事Aを読んで、念のため記事Bも読んでみたものの期待外れだったので、読むのをすぐやめたと考えられます。
実際にはユーザーの行動はもっと複雑です。記事を読んでる間に、リンクをたどって別の記事を読むかもしれません。再度、別のキーワードで検索するかもしれません。
そのような一連の行動を分析して、ユーザーがどの記事に満足しているのかを判断しているわけです。
良い記事は読者にアクションを起こさせる
では、どのようなユーザー動向データが、良いと判断されるのでしょうか?
それはユーザーが何かアクションを起こした時です。
例えば、ある記事が5分間読まれたとします。しかし、同じ5分間でも、画面を徐々に下にスクロールさせて、一番下まで行ったのと、最初に画面を開いて、そのまま5分間経ったのとでは、全然意味が違いますよね?
前者はしっかり読まれたと判断できますが、後者は画面を開いただけで放置されていたと考えられます。
もし記事中の関連記事のリンクがクリックされたとすれば、読者は興味深く読んでいると考えられます。
このように、良い記事というのは、読者に何かのリアクションを起こさせるものです。
では、どのようなアクションが、評価につながるのでしょうか?
次はそれを具体的に見ていきましょう!
良いユーザーアクション
良い記事だと判断されるためには、ユーザーにどのようなアクションを起こさせれば良いのでしょうか?
Googleは良いユーザー動向データが何かは、公表していません。そのため、ここに挙げたのは、あくまでも私の推測です。
しかし、私たちが普段どのようにインターネットを利用しているのかを想像すれば、このようなことが良いアクションだと自然に分かると思います。
- じっくりと読まれる
- ブックマークに追加する
- 他の記事を読まれる
- 同じユーザーが再訪している
- SNSでシェアされる
- コンバージョンされる
- 記事内の動画が再生される
それぞれがなぜ良い行動と言えるのか?
順番に説明していきますね。
じっくりと読まれる

まず一番大事なのは、その記事が最後までじっくりと読まれることです。
具体的には滞在時間が長いことと、ちゃんと最後まで読まれていることです。
画面を開いて放置された状態では、じっくり読まれたとは言えません。
ブックマークに追加される
ブックマークにへ追加されるということは、読者がまた読みたいと思っているわけです。
それだけ、興味を引く良いコンテンツだと判断されます。
他の記事を読まれる
ブログ内のリンクをクリックして、他の記事を読まれるのも、良いアクションです。
別の記事を読むという行為は、それまでの目的が達成されたからです。
また、別のサイトに行かずに、同じブログ内の別のコンテンツを読むのは、そのブログ自体を信頼してくれていると考えられます。
同じユーザーが再訪している
同じ記事を何回も読んでくれるというのは、その記事が役立つと考えられているからです。
同じユーザーが何回も読んでくれるのは、その記事やブログ全体が信頼されている証です。
SNSでシェアされる

人がSNSなどでシェアするのは、有益な情報を他人に伝えたいからです。
記事内のSNSのシェアやいいねボタンが、クリックされるのは、シェアしたいほど良いコンテンツだからと言えます。
コンバージョンされる
コンバージョンとは、次のような行為をユーザーがすることです。
- 商品が売れる
- メルマガに登録される
- お問い合わせメールが送られる
ユーザーは何か目的があって、記事を読んでいます。
そのため、コンバージョンが起きるということは、その目的が達成されたか、達成するために役立ったと判断されます。
記事内の動画が再生される
記事内に埋め込まれた動画が再生されることも、プラスになります。
役に立つ情報が存在する動画だから再生されたと判断されるからです。
また、動画を再生している時間の分、滞在時間が延びる効果があります。
このように基本的にどんなアクションでも、プラスに判断されます。
アクションを起こしているのは、ユーザーが興味を持って積極的に情報を欲しがっているからです。
だから、見方を変えれば、ユーザーにリアクションを起こさせることを、意識した記事作りが大切になるのです。
次はアクションを起こさせる、記事の作り方を紹介します。
ユーザーにアクションを起こさせる方法
ユーザーにアクションを起こさせる一番良い方法は、価値の高い情報を書いた、魅力的な記事を作ることです。
まぁ、当たり前のことですよね…。
何が良い記事なのかは、このあたりの記事に詳しく書いているので、まずはこれを読んでおいてください。
記事を書く準備で最も重要なのは、キーワードの背景にある検索意図を調べることです。 検索意図が把握できていると、ユーザーの満足度が高い記事を書くことができます。 そのため、検索意図を把握することは、最も強力なSEOなのです。 そこで、この記事では、キーワードの検索意図の調べ方を解説します。
ここでは、良い記事の書き方ではないく、テクニック的な視点で、ユーザーのアクションを促す方法を紹介しますね。
読みやすくて自然な流れにする
例えば、この記事は“ユーザーにアクションを起こさせることの重要性”を解説しています。
そのような記事なのに、最初にいきなりユーザーにアクションを起こさせる方法を解説しても、読者はなぜそれが効果的なのかピンときませんよね?
この記事の場合は、最初にユーザーのアクションが、SEO上プラスになる理由を説明した方が、話の流れとして自然です。
このように記事全体に、自然な流れを作ってあげることで、ユーザーが最後まで記事を読む可能性が高くなります。
論理破綻をなくす

例えば、この記事では、前半で”ユーザーにアクションを起こさせた方が良い”と書いていますが、後半で”ユーザーにはすぐにブラウザを閉じさせた方が良い”なんて矛盾したことを書いていたら、読者は混乱しますよね?
これは論理破綻と言って、読者にとって大きなフラストレーションを生み、離脱を招きます。
また、もし、この記事に”ユーザーにアクションを起こさせれば、必ず1位が取れる!”なんて書いてあったらどうでしょう?必ずしもそうなるわけではないので、こんなのはデタラメです。
これは論理飛躍といって、読者の信用を無くし、やはり離脱を招きます。
このように非論理的なことを記事に書かないように、十分注意してください。
操作性を意識した構造にする
動画の閲覧やSNSでのシェア、記事内のリンクのクリックなどもプラス評価される可能性のあるアクションです。
このようなアクションを起こしてもらうためには、ボタンやリンクがクリックされやすい状態になっていることが大切です。
画面内をスッキリさせて、ボタンやリンクを目立つようにしたり、記事を読んだ後にすぐクリックできる場所に、ボタンやリンクを配置すると効果的です。
ユーザーの操作性を意識した、デザインになるように調整してみてください。
まとめ
SEOというと、キーワードの使い方や、被リンクばかりを重視してしまいがちです。
でも、良い記事というのは、人間を満足させている記事です。キーワードや被リンクも大事ですが、最終的に大きく影響してくるのは、ユーザーがあなたの記事をどのように読んでいるのかです。
そして、良い記事であることの証が、ユーザーがアクションを起こしていることです。
記事を書く時には、是非こんなことに気を配ってみてください。
- いつのまにか最後まで読んでいるような自然な流れの文章を書く
- ボタンやリンクがクリックしやすいデザインにする
- 価値の高い情報が書かれた記事を作る
時間が経てば経つほど、ユーザーにどのように読まれているのかが、記事の順位に影響してきます。
細かいテクニックではなく、ユーザーに愛される記事作りを意識してみてくださいね!