
どうも、GELアドバイザーの齋藤(@Saito_Yoichi)です。
ちょうど良いライフスタイルとか、ちょうど良い働き方を考えてばかりいる私ですが、ある日、ふと疑問に思いました。
それは「江戸時代の仕事ってどんなだったんだろう?」というものです。
きっとこのブログを読んでるあなたも、毎日、頑張って頑張り過ぎなくらい、働いている人ではないでしょうか?
江戸時代と言えば、経済も産業も、今とは比較にならないくらい乏しい時代です。そんなに頑張る必要のある仕事が無かったように思いますし、貧しいからこそあくせく働いていたかもしれません。
そんな現代の私たちと比較して、江戸時代の人の仕事ぶりってどうだったんでしょうか?忙しい毎日を過ごしていると、ちょっと興味が湧いてきませんか?
というわけで、今回は江戸時代と現代の仕事のどちらが楽かを調べてみました!
もくじ
江戸時代の仕事
江戸時代と現代の仕事の比較といっても、昔も今も様々な職業や働き方があります。
江戸時代の仕事ぶりを調べてみると、やはり身分によって、かなりの差があるようです。
というわけで、江戸時代の身分の分け方である、士農工商のそれぞれの働き方を調べてみました。
武士

まず、武士ですが、一言で武士と言っても、かなり違いがあります。
例えばざっくりと分けると次のようになります。
- 将軍
- 幕府の役職
- 旗本
- 御家人
- 藩主
- 家老
- 藩士
この中でも、階級によって働きぶりは全然変わってきます。
将軍、藩主、役職持ちの武士は、長くても1日3時間前後の労働時間だったようです。

もちろん、禄高も高いので、とっても良い生活でした。
ただし、勘定奉行のような事務職をやる武士の場合は、昼から夜まで6時間前後働いたそうです。
とは言え、そんな階級の武士なんてごく一部です。
一般の武士になると、労働時間は更に短いものの、禄高も低いので、それだけでは生活できなかったそうです。
さらに、武士の家では、お城勤めができるのは、長男だけです。次男以下は自分で働いて、稼がなくてはいけません。
しかし、武士たる者が、卑しい仕事をすることは、幕府が認めていませんでした。
武士がやっても良いと認められていた、僅かな職業には、このようなものがあったそうです。
- 寺子屋などでの先生業
- 剣術指南
- 農業
農業もやって良いというのは意外ですよね。
でも、商人のようなお金稼ぎをすることは、見つかると切腹もあり得る重罪だったそうです。
お金稼ぎは卑しいことで、武士にあるまじき行為とみなされていたからだそうです。
寺子屋や剣術道場の仕事も限られます。そういうわけなので、多くの武士は、貧乏な生活を強いられていたようです。
農民
武士からの厳しい年貢の取り立てで、さぞや苦しい仕事のようなイメージなのが、農民・百姓ですよね。
確かに天災などによる、飢饉が起きた時なんかには、餓死するほどの危機に陥ることもありました。
でも、そんなのはごく稀な出来事です。実は江戸時代のお百姓さんは、かなり良い暮らしをしていました。
まず、農民には村ごとに自治権が与えられていて、武士が村に立ち入ることはありませんでした。年貢は村ごとにまとめて収められるので、武士は細かい内訳までは気にしません。
武士から厳しく扱われていたかと思いきや、実は割と気楽だったんです。
また、今の税率と言える、年貢率は”五公五民”といって、ぴったり50%でした。この数字だけだと、もの凄い重税に感じますよね?
ところが、年貢の基準になる検地は滅多に行われないため、農地の広さは、開墾すれば広げることが可能でした。当然、新しい農地は年貢の計算範囲外です。
また、農業技術が発達して、付加価値の高い作物なども作れるようになり、さらに収益性が上がります。なかには農業以外の仕事で、お金稼ぎをする人もいたそうです。
そいういった副収入も含めると、実際の税率は十数%程度だったそうです。現代の所得税とさほど変わらない税率だったんですね。
そういったわけで、農民は割と経済的な余裕がありました。
さらに農民が忙しいのは、田植えや収穫などの農繁期のみです。
それが終わった後の30日~40日程度は、お休みになり、歌舞伎や相撲、お祭りなどの遊びやお祭りが行われていたそうです。
なかには博打などで、借金を作り土地を奪われて没落するような人もいたんだとか、
博打なんかをやれるくらい、余裕のある生活をしていたのが、江戸時代の農民だったのです。
職人と商人

士農工商なんて言いますが、江戸時代は”工”と”商”の区別はあまり無く、両方ひっくるめて、町人という扱いだったそうです。
そこで、ここでは”工”を職人、”商”を商家やそこに奉公する人として説明しますね。
まず、職人です。一言で職人といっても、職業は様々です。
大工や左官など、主に外に出かけていく職人と、畳職人や刀鍛冶、着物を織る機織り、傘職人、絵師など、家の中で仕事をする職人の2つに分かれます。
外に出かける職人の場合は、朝から日が暮れるまで仕事をしますが、悪天候の時には仕事はお休みです。
家の中で仕事をする職人の場合は、自分が好きなだけ仕事をします。天気も関係ありません。
職人といっても、どれだけ働くかは注文の量や、天気などに左右されるので、人それぞれだったようです。
一方の商家やその奉公人はというと、まず商家の主や番頭さんのような人たちは、基本的に朝から日が暮れるころまで商売をします。
しかし、奉公人の場合は、午前中で仕事が終わってしまい、後は自由です。別の仕事をする人もいれば、近所の手伝いをする人もいたとか。
さらに真面目に働いていれば、番頭に取り立ててもらうなど、出世できる可能性もありました。
今のサラリーマンに近い働き方ですが、実態はとっても、楽だったようです。
実は農民が一番楽だった!

江戸時代の人々の職業を見ていて、何が一番楽だと思うでしょうか?
奉公人も良いですが、私はやっぱり農民が一番良さそうだなと思ってしまいました。
長期休暇が年に何回も取れる上に、比較的余裕のある生活ができます。農業は一年中作物の手入れに追われる仕事です。それにもちろん、農業収入は天候に大きく左右されます。それでも一番人間らしい生活ができるような気がする農民になりたいなと思いました。
その一方で、一番身分の高く、カッコいいイメージが強い武士は、最も生活苦に陥りやすい職業です。
職業選択の自由も無いので、私は最もやりたくないなと思ってしまいました。
本当に意外ですね!
では、今度は現代の働き方と比較してみると、どっちが良いのでしょうか?
今度は現代の働き方を考えてみます。
現代の働き方は何が良い?
江戸時代の農民は、実は余裕がある生活をしていました。あまりに遊び過ぎて、領主から倹約令が出るほどだったそうです。
でも、今の農業はどうでしょうか?
農業は儲からなくて、大変というイメージですが、平成26年のデータでは、年々減少傾向にあるものの、農家の収入額は、全国平均で456万円だったそうです。
やはり収入額は畑の広さに比例するようで、北海道の農家の平均収入額は750万円程度だそうです。
大変なイメージですが、意外に収入額は多いですよね?
しかし、もちろん新規就農者が平均額の収入を得られるかと言うと、それは難しいようです。
また、昔も今も変わらず、農業は一年中作業が続く大変な仕事です。ある作物の収穫が終わったら、また次の作物に取り掛かるという作業の繰り返しの仕事なのです
江戸時代版のサラリーマン、奉公人のような働き方は、今では単なるパートです。そのような働き方では、十分な収入が稼げそうもありません。
じゃあ、職人はどうなのかというと、現在は大規模効率化が進んでいます。昔の職人が作っていた品物の多くは、大企業が安くてそれなりの物を作って売っています。
現代では、普通の職人では仕事にならないわけです。

じゃあ、やっぱり普通にサラリーマンをするしかないんでしょうか?
しかし、それは最も過酷な働き方かもしれません…。
この記事にも書いてますが、現代のサラリーマンは、見方によっては、ローマ帝国時代の奴隷よりも過酷な働き方と言っても過言じゃありません。
現代の日本でサラリーマンとして働くのは大変です。 中には奴隷のようだと感じながら、サラリーマンを続けている人もいるかもしれません。 では、実際にサラリーマンと奴隷を比べたらどうなんでしょうか? ここではサラリーマンと奴隷の違いを考えてみます。
とは言え、大企業の性質として、採算が取れない事業や商品はどんどん廃止していきます。大多数の人のニーズを満たす製品やサービスを作った方が儲かるので、少数の人のニーズは、無視されがちです。
そのような大企業が見向きもしない、隙間のニーズを満たす職人的な働き方ができたら、良いのかもしれませんね(^^)/
それには、今までにない新しいアイデアが必要ですね。ハードル高いですね~(^^;
ちなみに私のナリワイである、ブログ運営も参入障壁の低さから、どんどん始める人が増えています。決して気を抜ける楽な仕事じゃありません。
やっぱり、江戸時代の農民になりたいな…。
まとめ
というわけで、今回は江戸時代と現代の仕事を比較して、そこからどんな働き方をすれば幸せになれるか考えてみました。
江戸時代の仕事の内容をもう一度簡単に振り返ってみますね。
- 武士
- 農民
- 職人・商人
下級武士は収入がなく、しかも職業選択の自由が無い!もっとも貧困に陥りやすい身分。
年貢率は50%だが、実質の税率は十数%と現代とあまり変わりない。そのため、比較的経済的に余裕がある上に、農閑期は長期休暇があった。
様々な職業があり、その職業によって、働き方も様々。仕事さえあれば、幸せな生活ができる身分だった。
こうしてみると、現代でも本質的に農業という働き方は同じなはずなので、上手にやれば、幸せな生活ができそうですよね?
なぜ、現代の日本では、農業従事者がどんどん減ってるんでしょうか?日本の農業もなんとか盛り返して欲しいですよね?
いずれにせよ、今の日本では隙間のニーズを狙った職人的な働き方をすることが良さそうです。
あなたも勇気を持って一歩踏み出して、新しい生き方を探してみてください!

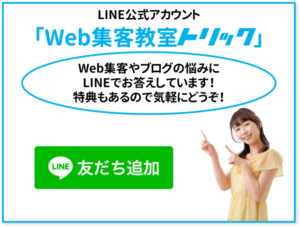


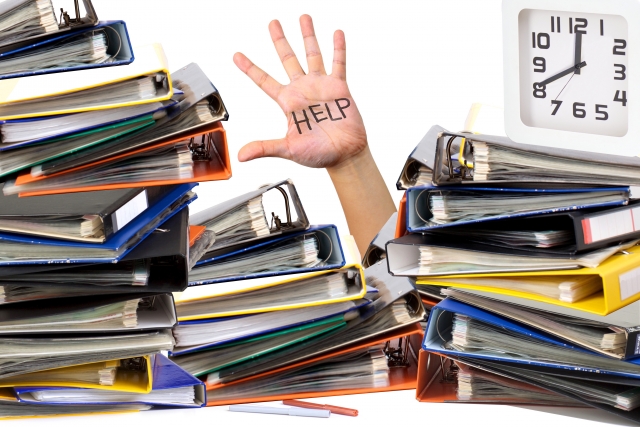




ブログ読みました。
現代社会はいかにお金を使わせるか考えられている世の中だと思います。低所得者は現代的な生活を捨てて生きた方が幸せですよね!?
清水さん
記事を読んでいただきありがとうございます。
> 低所得者は現代的な生活を捨てて生きた方が幸せですよね!?
実は私も昔はそう考えていました。
でも、実際にお金を使わずに生きていこうと思っても、それは意外と難しいことに気付きました。
現代人は全てお金への依存度が高いと思いますが、だからと言って、依存を完全に断つのも難しいのだと思います。
だから、重要なのは、自分の限界までお金への依存度を下げることだと思ってます。
もちろん、山奥で仙人みたいなライフスタイルをしても、何の苦も無いのであれば、それが理想的だとは思いますけどね(^^)/